法人税の基本的なしくみについて説明させて頂きます。
申告書、届出書類は国税庁HPを参照してください→法人税申告書の記載の手引き(H29年度版) |
|
|
|
- Ⅰ.法人税はどんな税金か
- ① 法人税は「所得に課税」されます
- 法人税とは、会社などの法人が、その事業を通して得た所得の中から支払う税金であ り、広い意味での所得税の一種です。 → 所得とは
- ② 法人税は「国税」です
- 税金は、国に納める「国税」、都道府県や市町村に納める「地方税」とに分類されますが、法人税はこのうち「国税」にあたります。
なお、法人の所得の中から支払う税金には、国税としての法人税の他に、地方税としての「住民税」と「事業税」があります。
- ③ 法人税は「直接税」です
- 税金を納める者(納税者)と、税金を負担する者(担税者)が同一である税金を「直接税
」といいます。反対に、納税者と担税者が異なる税金を「間接税」といいます。
法人税は税金を負担するのも納めるのも法人となりますので、「直接税」になります
- ④ 法人税は「申告納税方式」の税金です
- 税金を納税者が計算して、納税者が申告・納付する方法を「申告納税方式」といいます。
税金を課す国や地方公共団体が税金を計算し、納税者が税金を納める方法を「賦課課税方式」といいます。
法人税は納税者である会社が自ら税金を計算し、申告・納付する為に「申告納税方式」に
なります。
|
|
|
Ⅱ.法人税の種類
- ①.各事業年度の所得に対する法人税
- 法人の毎期の事業活動によって得られる所得に対して課される法人税です。
- ②.各連結事業年度の連結所得に対する法人
- 企業グループを1つの納税単位として法人税を計算する、「連結納税制度」を採用した場
合に、「各事業年度の所得に対する法人税」の代わりに課される法人税です。
- ③.特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
- 主に、信託会社を対象とする法人税で、特定の資産を運用する信託に対して課される法人税です。
- ④.退職年金等積立金に対する法人税
- 退職年金業務等を営む信託会社や保険会社などを対象とする法人税です。
- 退職年金に対する課税が、従業員が退職するまで発生しないことに対する遅延利息たる性質を持つ法人税です。
■注:H29年3月31日までに開始する事業年度については課税停止となっています。
一般的な会社では、会社の設立から解散までは、①の「各事業年度の所得に対する法人税 」が課されます。
②から④までは、大きな会社、もしくは特殊な会社に係る法人税となります。 |
|
|
|
Ⅲ.法人税が課税される法人とは
- 法人の種類は様々ですので、法人の目的や特性により、「課税される法人」と「課税されない法人」があります。
| 種 類 |
法人税 |
課
税
さ
れ
る
法
人
|
①普通法人 |
株式会社・有限会社・医療法人・相互会社・企業組合・日本銀行など |
全所得が原則、課税されますが、中小法人(期末資本金が1億円以下の法人)は税率が軽減されています。 |
| ②協同組合等 |
農業協同組合・信用金庫・労働者協同組合など |
原則、法人税が課税されますが、税率が軽減されています |
課
税
さ
れ
な
い
法
人
|
①公共法人 |
地方公共団体・金融公庫・事業団など |
「非課税」となっています |
| ②公益法人等 |
社団法人・財団法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人など |
原則、「法人税は非課税」となっていますが、収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。 |
③人格のない
社団等 |
PTA・同窓会・実行委員会など |
人格のない社団は法律上の法人ではありませんが、税法上は法人とみなされ、収益事業から生じた所得には法人税が課税されます。 |
補足・・・収益事業とは
法人税法上の収益事業とは、次の34種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。
この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業 (16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業 |
|
|
|
Ⅳ.法人税の計算の仕組み
- ①.課税対象となる所得とは
- 法人税は、会社の利益ではなく所得(これを「課税所得」といいます)に課税されます
商法による企業会計では、収益から費用を差し引いて利益を求めます
税法による税金計算では、益金から損金を差し引いて所得を求めます
会社の所得に対して課される法人税は、「所得金額(課税標準)×法人税率」です。
収益と益金、及び費用・損失と損金の額について、大部分のところは「一般的に公正妥当と認められた会計処理の基準」で処理されていれば
-
- となります。
- しかし、税法では、課税の公平を図る目的や租税政策、産業政策上の目的で、収益に加算したり(益金算入)、減算したりするもの(益金不算入)、費用・損失に加算したり(損金算入)、減算したりするもの(損金不算入)を別に規定して、所得を計算することとしています。
- これらの規定されているものを税法上の「別段の定め」といいます。
- したがって、「別段の定め」に該当する取引がある場合には、その法人の利益と所得の金額は一致しないことになります。
- また、税法上の「別段の定め」を基礎に、所要の加算または減算を行って所得の金額を求めることを「税務調整」といいます。
- 「税務調整」事項の主なものは下記のとおりです。
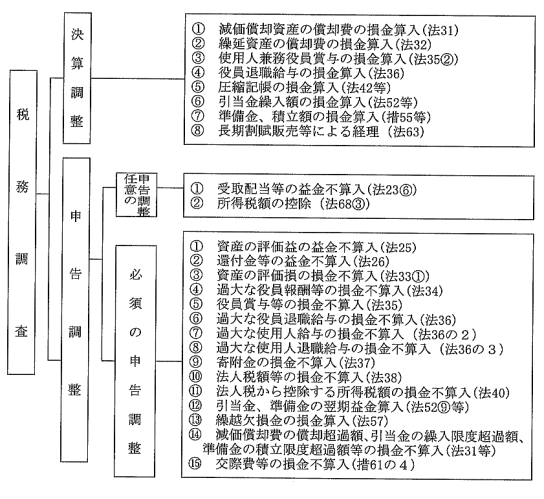
- ②.法人税の税率は
国税庁HP参照→法人税の税率に関する改正PDF/172KB
- ③.計算期間(事業年度)
- 法人税は、会社の所得に対して課税されます。
- 会社の営業活動は途切れることなく行われている為、活動期間に区切りをつけて「所得」の計算をする必要があります。
法人税ではこの「所得」を計算するための期間を「事業年度」といいます。
事業年度は、法人の定款、寄附行為、規則、規約などで定めます。
|
|
|
- Ⅴ.納税地と申告・納付
-
- ① 納税地
-
- 法人税の申告・申請・届出・納付をする場合の基準となる場所を「納税地」といいます。
- 会社の納税地は、原則として本店又は主たる事務所の所在地になります。
本店が変更した時には、変更前の所在地の税務署長と、変更後の所在地の税務署長の双方に、異動の届出をしなければなりません。
また、登記された本店の所在地に、実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長がしかるべき納税地が指定される場合があります。
- ② 申告・納付
- 法人は、原則として期末(事業年度末)から2カ月以内に、確定申告書を作成して所在地の税務署長に提出しなければなりません。
- そして、確定申告書の提出期限までに法人税額を納付しなければなりません。
|
|
|
※税法の改正や個々の事情により掲載の内容と異なる場合があります。
個別の案件に関しましては、税理士にお尋ねください。 |
|
| 前のページへ戻る |
トップページへ |
|